ゼミ詳細
日時:2025年3月15日(土)18:00~19:30
主催:東京理科大学工学部建築学科
参加方法:オンライン
参加人数:会場170名程度・オンライン80名程度
レポート
はじめに
哲学者カントは、人間とは何かという問いに【認識・判断・実践】というキーワードを用いて向き合いました。坂牛先生は【認識・判断・実践】を建築の言葉に置き換えて、以下のように表現されました。
認識すること=見ること
判断すること=書くこと
実践すること=作ること
【見る】とは実際に何かが見えるということではなく、どう捉えるかという受け取り方のことです。
【認識力】を豊かにすることで、【判断力】が豊かになり、やがて豊かな【実践】に至ります。坂牛先生は人間としての能力すべてを使って建築と向き合っています。
見ること
▼文学部で建築を教えるという経験を通して
建築を専攻していない(建築をまったく知らない)人に対して、どうやって建築を説明するか? という課題があったそうです。【建築らしい論理=内在する論理】と【建築の外側の論理=外在する論理】という二つの視点を用いて建築を説明することで、この課題に向き合いました。
【内在する論理】と【外在する論理】から建築を考えるために、10年以上続けてこられたのが輪読です。
数人のグループで一つの本を読み解釈し、お互いに意見を交わす読書方法を輪読といいます。
▼輪読ゼミ
輪読ゼミでは建築本と建築以外の本を輪読本として採用し、一年間で25冊くらいを読みます。
また、輪読本には【垂直的思考=内在する論理】によって書かれた本と、【水平的思考=外在する論理】によって書かれた本が採用されていました。
- 垂直的思考:哲学、美学といった、対象そのものに内在する論理のこと
- 水平的思考:対象の外側に存在する論理によって、対象の解像度をあげていくための思考のこと
以下はとある年の輪読本の一部です。
垂直的思考によって書かれた建築らしい建築本
- ハリー・F・マルグレイブ『現代建築理論序説』
- ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』
- 篠原一男『住宅論』
水平的思考によって書かれた建築の外側から建築を書いた本
- 大月敏雄『町を住みこなす』
- 門脇耕三 他『シェアの思想』
垂直的思考によって書かれた本
- 岩内章太郎『新しい哲学の教科書』
- 福岡伸一『生物と無生物のあいだ』
- 日高敏隆『チョウはなぜ飛ぶか』
- 橋爪大三郎『初めての構造主義』
水平的思考によって書かれた本
- 北田暁大『広告の誕生』
- 東浩紀『動物化するポストモダン』
- 橋爪大三郎『正しい本の読み方』
私は輪読ゼミを通して、【垂直的思考】から建築論理を学び、【水平的思考】をすることで多様な視点を持ち、建築論理の解像度を上げていくことができたように思います。
何かの専門分野を学ぶ際、専門的な用語・論理といった内在する知識のみ覚えていっても応用が効かない。自分の外側に知識を拡張して何かを作り出すためには、専門外の知識から関連付けて考える視点も必要だということを学びました。
書くこと
▼多様な視点で建築を見る
坂牛先生は【垂直的思考】と【水平的思考】という両極の視点に10年以上触れることで、どちらにも足を付け中庸をとり、多様な視点で建築を見るようになったそうです。
常に中庸をとる【見方】をし、建築について【書く】ことを実践されました。
- 『建築の規則』を出版 (2008年):【垂直的思考】で建築について書いた本。建築に内在する概念で建築の設計を説明した。
- 『建築の条件』を出版 (2017年):【水平的思考】で建築について書いた本。建築に外在する概念で建築の成立を説明した。
作ること
▼窓を作る
窓の在り方について考えた建築を多く設計されました。
- 柱・壁を作ることから建築は始まった。柱・壁という大前提に操作を加えない
⇒壁に穿たれた窓・壁と壁に挟まれた空間を作ろう - 人間は建築に慣れるものだが、建築ができた時の新鮮さが消えてしまうのはもったいない
⇒窓の外は毎日移り変わる。この変化を大切にしたい - 窓はいろいろなものを誘導するもの。生気に満ちている場所を作ろう
- 連窓の家#1 (2000年)
- 連窓の家#2 (2001年)
- 連窓の家#3 (2001年):窓を縦横に伸ばした建築
- ホタルイカ (2003年):足元の窓を伸ばした建築
【壁=地】に穿たれた【窓=図】を操作することで、図と地のバランスが崩れるギリギリを攻めた。
窓にはガラスがはまっているが、必ずしもはめる必要はないのではないか? 窓をフレームにすることで生気が行き来する場所を作ることに。
- するが幼稚園 (2005年)
雨除けスクリーンに開口(フレーム)を開けた建築。フレーム一つ一つに特別な意味づけをせず、均一に【園児の遊び場】という役割を持たせている。
- 内の家 (2013年):何かをフレームするという特別な意味づけを行った。(公園をフレームするための窓、吹き抜けをフレームするための空間)
- 松の木のあるギャラリー (2013年):大きな開口が庭に開く
▼流れと淀みを作る
フレームは建築という物体を作る要素の一つだが、最も大切なのは建築を通過する人や物ではないか? という気づきから、【流れと淀み】を作ることが近年のテーマとなりました。
建築を通過するスピードが速ければ【流れ】、遅ければ【淀み】になると定義しました。
- 富士見の小屋 (2022年)
- Mt.fujiジビエ加工センター Dear Deer (2024年)
1枚の板が流れを作っている建築。
▼【作る】を通して、【書く】ことを続ける
- 『建築の設計力』を出版 (2020年):建築は物と間と流れでできている。また、流れは建築の内在的要素であると同時に外在的要素でもある。
- 『世界としての窓』を出版 (2024年):平瀬有人との共著。流れとフレームについて書いた本。
- 『建築を見る技術』を出版 (2025年):【見る】ことについて書いた本。
感想
私は2019年3月に、東京理科大学工学部第二部建築学科坂牛研究室を卒業しました。卒業してからもう5年以上が経ちます。意匠設計のエスキスをしていただいた3年間、研究室配属を経てより深く先生にご教授いただいた1年間を思い出す時間となりました。
先生が話された、何かを【見る】時の視線の在り方、見方が豊かになることで【書き】、【作る】ことで何かを表現したくなる人間の性質に気づかされました。
私は建築デザインの世界から離れてしまいましたが、何かをデザインする者として【見る・書く・作る】の実践を自分なりに行っていけたらと思います。なんだか生きることがこれからもっと楽しくなりそうです!
昔から変わらず、生き生きと建築を語る先生の姿を拝見でき、とても励まされ嬉しい気持ちでいっぱいになりました。この度は貴重な最終ゼミの様子を公開してくださり、大変感謝しております。ありがとうございました。
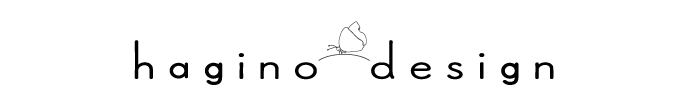
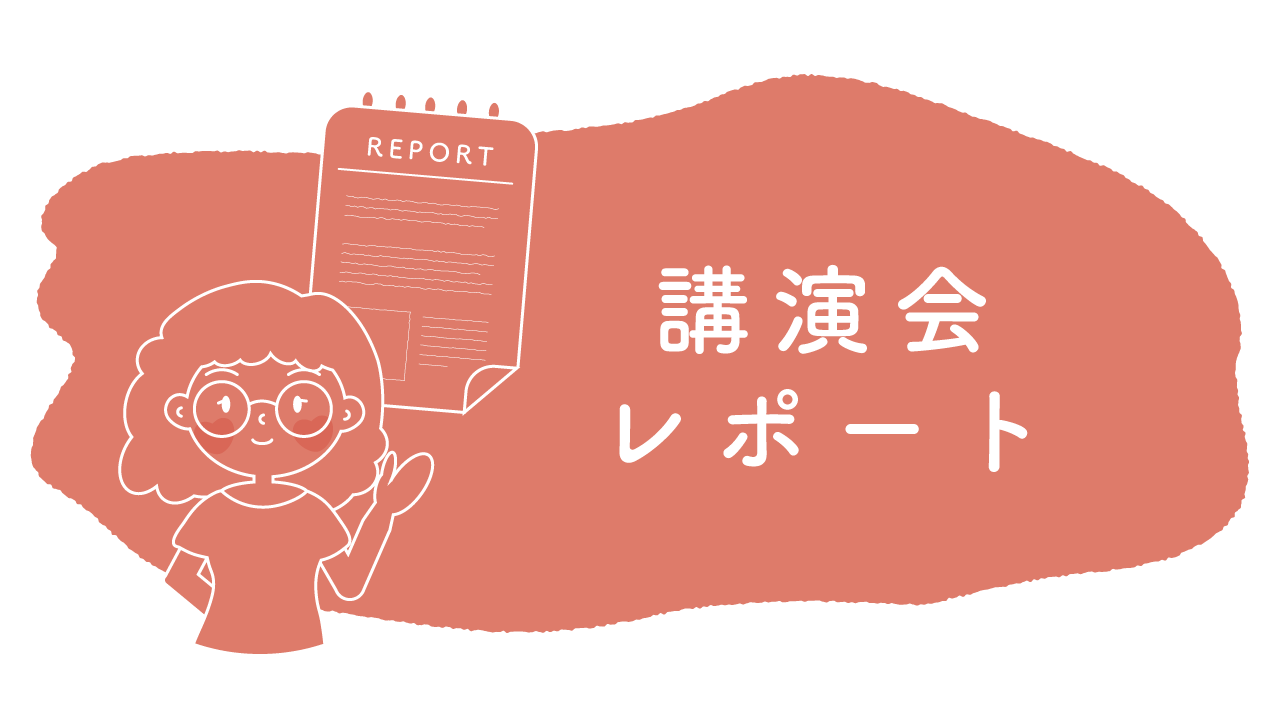


コメント