デザインはアートではない
▼アートとは
人の精神・感情など心を動かす作品のことをアートと呼ぶ。(ex.絵画、彫刻、音楽…)
ちなみに…芸術よりも『アート』の方が現代的で、親しみやすい印象を持つ人が多いそう。制限のない状態で自己表現をすることとも言える。
▼デザインとは
目的を設定して、計画し、表現する一連のプロセスのこと。
他者(ユーザーや社会)にとって価値ある目的を設定し、それを達成するための計画を立て、他者が理解できる仕様として表現すること。また、デザイン力は習得することが可能。
アートとデザインはどちらもビジュアルを作り出すものであるため混同しやすいが、制作過程の思考方法が全く異なるため、良いデザインを作るためにはアート思考からデザイン思考への切り替えが大切。
▼デザインに向いている人
オリジナリティを出せる柔軟な発想力、美的感覚、時代感覚があると◎
実際は地味な単純作業も多いので、地道に作業を続けられる忍耐力、自分のデザインやアイデアを他者に主張する説得力も必要。
▼デザインはどこまでがパクリ?
見た目をパクるのではなく、根底にある表現プロセス(何を目的にしているか?)をパクると良い。
デザインは目的が一緒のことも多いため、似ている成果物が出てきてしまうことも多い。盗作に明確な基準は無いが、誰が見てもこれは似すぎているという見た目はアウト。
デザイナーに必要なスキル
▼デザイン力を磨く
優れたデザイナーには、分析力・デザイン知識・発想力・情報収集力・情報整理力・課題解決力を用いて形にする能力があり、実はセンス(感覚的なもの)はあまり重要ではない。
デザインを磨くために以下の5つのポイントを大切にしよう。
- 自分の感性を見直す(自分の感性が人とズレてる?→軌道修正が必要)
- さまざまなデザインに触れる
- 相手(ターゲット)のことを考える
- 単純に考えられるように整理する
- デザイナーの思考法を参考にする
▼言語化する
相手が分かるようにまとめて分かりやすい言葉に変換して伝えるためには、自分の頭の中をシンプルに整理する必要がある。
言語化によるメリットは以下の通り。
- アイデアの一貫性を保つことができる→人間は忘れやすく最初に考えていたアイデアからかけ離れてしまうことがよくある。言葉として目に見える形にしておくことで、アイデアを何度も思い出し、頭の中に定着させることができる
- 自分の思考を客観視できる→なんでイライラしているんだろう?なんでこれを作ったんだろう?自分はこんなことを考えていたんだという気づきが大切。アイデアの穴に気づき、より洗練させることができる
- 要約力が身につく→文字起こしして声に出してみる。何を伝えたいのか、一言で正確に伝えるのに効果的な表現方法が分かってくる
▼デザイン論
デザインを作るために以下の3つの視点を持とう。
- レイアウト(重要度:7~8割):どこに何をどう置くか。(目立たせたいものは面積を大きくする・人間の目の構造上、左側に気持ち寄せたほうが真ん中に配置されているように見える・上側の情報の方が大きく見えるなどの理論を学ぶと良い)
- フォント:文字が見えなかったり、読み取れなくなってしまうとダメ。フォントは柄ではない
- カラー:デザインのイメージ(印象・雰囲気)を決める。色の理論についても学ぼう(色の領域は赤が一番大きいため、ちょっとの差で違う色に見えやすい。色領域の大きさ→赤>青>緑。 RGBカラーの方が再現できる色域が大きい。そのためCMYKに変換すると若干色が鈍るなど)
ディスカッション
▼テーマ『言語化について』
Q:言語化って何だろう?→言葉からアイデアを作成していく力? 出来上がったものに対して説明する力?
A:どちらの要素もある。自分が感じた感覚を言語化していく(ex.なぜ丸く配置したくなるんだろう?→みんなが集う感じを出したいからだ)
Q:デザイナーはすべて論理的にデザインの説明ができる。また、論理的に説明してくれるとクライアントは安心する。
A:クライアントのデータ管理は大切。この人はこういうところが気になって、ここで後戻りがあるだろうななどの予想をしておくのも良い。
回答:上司に承認を得なければならなかった。上司の期限が悪いと一生懸命プレゼンしても承認が得られないなどの実体験あり。期限が良いときに案を持って行ってプレゼンすれば良かったとも思った。
回答:感覚で作るのはデザインではない。しかし、感覚で作るときもある。感覚から作るとアートになり、理論から作るとデザインになるのではないだろうか。
回答:学生時代、建築デザインを学んでいた。一生懸命相手に説明してもなかなか伝わらなかったのは、建築をアートとしてとらえていたからではないだろうかと気づかされた。自分の感性・感覚を言語化して他者と共有することの難しさを実感していた。論理的な思考で他者を説得するデザインができるようになりたいと思った。
回答:自分は感性よりも理屈でとらえることのほうが多い。美術館に行っても感じるものは少ないが作品の説明を読んで理解が深まる。背景や理由付けに助けられている。
▼テーマ『センスを磨くために日々何を大切にしていますか』
回答:自分の持ち物を選ぶ際に、これが良いと思えるものを選ぶようにしている。なぜこれが良いなと思うのか・嫌いだと思う理由を深堀して考えている。
回答:自分の好きなことを知る。
回答:自分の感覚だけでなく、大衆の意見・感覚を知ろうとする。(みんなはこう考えるのか! 気づきが大切)
回答:受け入れられないと感じるデザインが流行りだしても拒絶しないようにしている
回答:アート・自己表現だけでなく、デザインにもセンスが必要なんだということに気づいた。『形が良い、色が良いなどの外側のセンス』と『人の心を動かすなどの内側のセンス』があり、奥が深いと感じた。
回答:デザインの本(デザインプロセスが載っているもの)を読んでみる。デザイナーの頭の中・思考が分かる。
回答:前職は目的がはっきりしているものを形にしてくださいという職場だった。そこに自分の感覚が入り込む余地が無かった。自分の内側の気持ち(感覚)が無いので、そこもバランスよく養いたい。
回答:自分がこうと思っても、相手ありき。言われたら取り入れなければいけない。
回答:センスを磨くってどういうことかよく分からない。言語化も苦手。言語化をAIに頼っても良い?
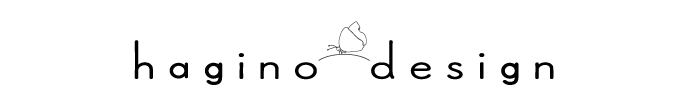
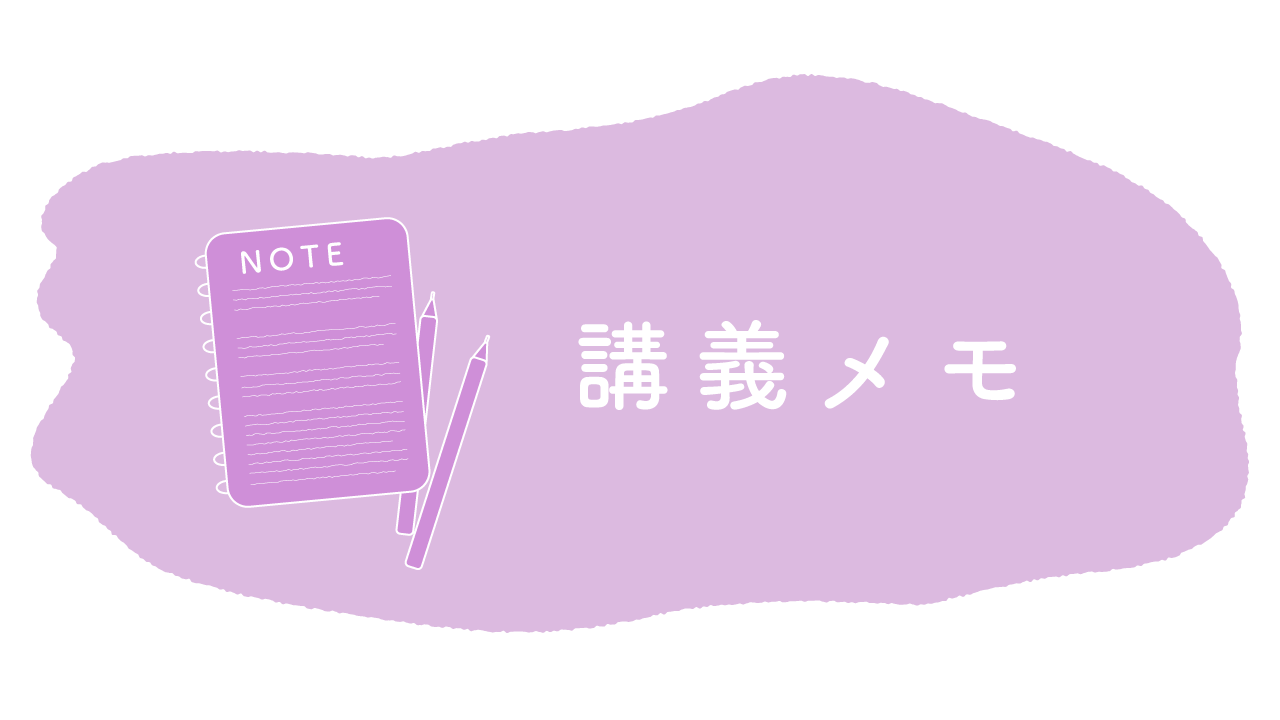


コメント